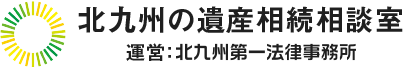被相続人が亡くなった後、相続人の一人が被相続人の預金を勝手に引き出して使ってしまっていたとします。例えば、亡くなった母名義の預金を、母の死後、子の一人が勝手に引き出して使ってしまっていたような場合です。この引き出した預金について、もともと被相続人の財産だったものとして相続財産に含まれないのでしょうか。
この点、遺産分割の対象となる財産は、原則として相続開始時に存在しかつ遺産分割時にも存在する財産です。そのため、これまでは、上記のような亡くなった後に引き出した預金があったとしても、原則として遺産分割の対象とはならないとされてきました。ただし、共同相続人全員の合意があった場合に例外的に遺産分割の対象とされてきました。
この扱いが、相続法改正において、明文化されました(民法906条の2)。
条文上、財産を処分した人の同意は必要ないとされたことがこの条文の注目点です。
つまり、これまでは、相続財産を相続人の一人が、勝手に処分(例えば預金を払い戻すなど)していた場合、その相続人が遺産分割調停の中で勝手に処分した財産を遺産分割の対象とすることを拒否した場合、遺産分割の対象に含めることはできませんでした。そのため、別途民事訴訟(不法行為に基づく損害賠償請求もしくは不当利得返還請求)を提起する必要がありました。
しかし、改正法によって、被相続人の財産を処分した人が同意をしなくても、他の相続人全員が同意した場合は、遺産分割の対象に含めることができるようになりました(906条の2第2項)。
ただし、これは処分をした人が誰かが認定できること、自己使用であることが認定できることが前提です。
例えば預貯金の払い戻しについて、誰がしたかわからない場合は、払い戻し手続きを行った書類を開示してもらい筆跡等を明らかにしたり、被相続人のキャッシュカードの保管状況等を明らかにするなどして誰が処分をしたかを明らかにする必要があります。
また、自己使用に関しては、被相続人の預金の払い戻しを受けた相続人の一人が、相続債務、公租公課、遺産管理費などの支払いをしたことを領収書などで示す場合は、自己使用とは認められず、遺産分割の対象に含めるのは相当でないとされます。
誰が処分したかは明らかであるケースが多いと考えられますが、自己使用に関しては認定が難しい場合があります。その場合は、やはり遺産分割の手続きの中で判断することは相当ではないとされます。そのためそういったケースでは従前とおり民事訴訟を提起する必要があります。
民法906の2ができたことで、相続人の一人が自己使用したことが明らかであるにも関わらず、その自己使用した財産を遺産の対象とすることを拒否することができなくなりました。
しかし、上記のとおり、誰が処分したか、自己使用したかに争いがある場合は、従前とおり訴訟が必要な場合があります。
どのような裏付け資料があるのか慎重に判断した上で、遺産分割調停の中で話し合いを行うのか、訴訟を提起するのか判断することが必要です。
電話:093-571-4688