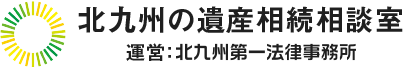寄与分・特別受益
こんなお悩みはありませんか?
- 長年、親の介護をしてきたが、他の兄弟と同じ相続分なのが納得できない。
- 兄だけが生前に親から土地や住宅資金を贈与されていた。
- 自分だけ親の事業を手伝ってきたのに評価されていない。
- 結婚資金をもらっていたことが特別受益に該当するか不安だ。
- 寄与分や特別受益の主張方法がわからない。
寄与分とは
寄与分とは、法定相続分だけでは報われない特別な貢献を評価し、相続における不公平感を解消する役割を持つ制度です。具体的な金額は、寄与の内容・期間・程度などを考慮して決めることになります。
亡くなった人の財産の維持・増加に特別に貢献した相続人がいる場合、法定相続分に加え、寄与分として追加の相続分を受け取れます。例えば、亡くなった人の介護や看護を長期間無償で行っていた場合や、亡くなった人の事業を手伝って収益増加に貢献した場合などに寄与分を受け取れる可能性があるでしょう。
寄与分が認められる要件
寄与分が認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 亡くなった人の財産維持・増加に貢献したこと
- 貢献した内容が「特別の寄与」といえる程度であること
- 貢献への対価を受け取っていないこと・または著しく低い対価で行われたこと
- 貢献した人が相続人であること
重要なのは、親族としての一般的な協力義務の範囲を越えるほどの貢献をしているかどうかです。同居している子どもが行う日常的な家事や世話の範囲では、寄与分は認められないでしょう。
特別受益とは
特別受益とは、相続人が亡くなった人から生前に受けた贈与や、遺贈など相続分の先渡しとみなされるものを指します。例えば結婚・独立資金の援助、住宅資金の贈与、生前に無償で不動産を譲り受けた場合などが特別受益に該当します。
特別受益がある場合、その相続人の相続分からは特別受益の金額分が差し引かれ、実質的な公平を図るのが一般的です。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。ただし婚姻20年以上経過した場合の持ち戻し免除など、例外規定もあるため、注意が必要です。
問題となる事例
寄与分と特別受益で問題となりやすいのは、まず評価額の算定です。特別な貢献があったとしてもそれをどのように金銭評価するか、生前贈与された不動産の価値をどう評価するかなどで意見が分かれることがあるでしょう。また「それは親孝行の範囲」「それは生活費の援助」など、寄与分や特別受益の存在自体が争いになるケースも多く見られます。
さらに立証が難しいという問題もあります。特に口頭での約束や現金贈与は証拠が残りにくいため、争いの原因となる可能性が高いです。当事務所では豊富な経験を活かし、適切な主張と証拠収集をサポートしています。
北九州第一法律事務所の特徴
北九州第一法律事務所は、北九州最大規模を誇る地域密着型の法律事務所として、50年以上にわたり地域の皆さまの法律問題を解決してきました。長年の活動で培った豊富な相談実績と確かな経験、ノウハウが私たちの強みです。
当事務所の弁護士は緊密に連携を取り、個々の知識や経験を共有しています。そのため、あらゆる相続に対して総合的な解決策を提供可能です。また各弁護士は他士業とのネットワークを持っており、相続に関連する多角的なサポートも強みとしています。相続でお悩みの際は、ぜひ北九州第一法律事務所にご相談ください。