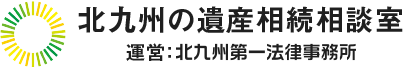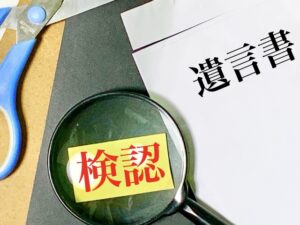
1 遺言書の「検認」(けんにん)を請求しなくてはならない場合
法律では、遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知ったあと、遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければならない、と定められています。
ただし、すべての遺言書について検認が必要ということではなく、公正証書による遺言のほか、法務局に保管されている自筆証書遺言(遺言書保管制度)については、検認の必要がありません。
つまり、遺言者本人などが保管している自筆証書遺言や秘密証書遺言が対象となります。
裁判所の令和5年度の統計によれば、検認の申立件数は全国で約2万2000件に上るようです。
2 遺言書の有効・無効を判断する手続きではない
このような検認の手続きは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止することを目的としています。
遺言書が有効か無効かを判断するための手続きではありません。
遺言書の有効性を裁判手続きで争うという場合、別に、「遺言無効確認訴訟」などを提起することになります。
3 検認を終えないと相続手続きは進められない
検認を終えると、家庭裁判所に申請すれば、検認済証明書を発行してもらえます。
遺言書の中で、預貯金や不動産、株式などの有価証券について遺言がされている場合、払い戻しや名義変更は、検認の手続きが完了していることを表す検認済証明書も必要となります。
そのため、検認を終えないと遺言書に記載されている相続手続きを進めることができないのです。
4 検認を請求しないと過料が課されることも
遺言書を提出せず、検認をしないまま遺言書どおりに財産を処分するなどした場合、あるいは、封印されている遺言書を自宅など家庭裁判所以外の場所で開封をした場合、5万円以下の過料が課されることがあります。
5 検認の手続きでは具体的にどのようなことをするのか
検認の申立てをすると、裁判所が検認を行う日(検認期日)を決定し、相続人に対して通知します。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の自由で、全員がそろわなくても検認手続は行われます。
検認期日では、申立人から遺言書を提出し、出席した相続人等の立会いのもと、裁判官が(封がされた遺言書については開封の上)遺言書を検認します。
6 早めにご相談ください
相続放棄(3か月)や遺留分侵害(1年)、相続税申告(10か月)など、期限の短い手続きにも影響する重要な制度です。
遺言書が見つかったとき、わからないことやご不安な点があれば、ぜひお早めにご相談ください。
以上
電話:093-571-4688